住民基本台帳による東京都の世帯と人口:毎年
調査年
- 令和7(2025)年
- 令和6(2024)年
- 令和5(2023)年
- 令和4(2022)年
- 令和3(2021)年
- 令和2(2020)年
- 平成31年・令和元(2019)年
- 平成30(2018)年
- 平成29(2017)年
- 平成28(2016)年
- 平成27(2015)年
- 平成26(2014)年
- 平成25(2013)年
- 平成24(2012)年
- 平成23(2011)年
- 平成22(2010)年
- 平成21(2009)年
- 平成20(2008)年
- 平成19(2007)年
- 平成18(2006)年
- 平成17(2005)年
- 平成16(2004)年
- 平成15(2003)年
- 平成14(2002)年
- 平成13(2001)年
- 平成12(2000)年
- 平成11(1999)年
- 平成10(1998)年
- 平成9(1997)年
- 平成8(1996)年
- 平成7(1995)年
住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成14年1月 概要(年齢構造指数)
5 年齢構造指数
年少人口指数は前年と同じ16.8であったが、老年人口指数は23.3と0.9ポイント上昇している。年少人口指数は昭和51年以降、低下傾向が続いていたが、平成12年以降は3年連続で同値となった。
一方、老年人口指数は調査開始以来一貫して上昇を続けており、14年は4.3人の働き手で1人を支えることになった。
従属人口指数は前年より0.9ポイント上昇し、40.1となり、働き手と働き手以外の比率は2.5対1となった。
老年化指数は平成8年に老年人口が年少人口を上回り、14年は前年より5.1ポイント高い138.6となり、20年前の39.9の約3.47倍になっている。
(表10,図5、参考表第7表参照(![]() Excel:35KB))
Excel:35KB))
(注)各指数は人口学における用語である。
年少人口指数=(年少人口)÷(生産年齢人口)×100
老年人口指数=(老年人口)÷(生産年齢人口)×100
従属人口指数={(年少人口)+(老年人口)}÷(生産年齢人口)×100
老年化指数=(老年人口)÷(年少人口)×100
※年齢構造指数とは、上記の指数の総称である。
表10 年齢構造指数の推移(昭和57年~平成14年)
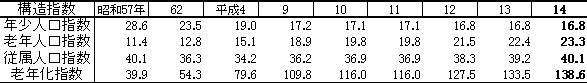
図5 年齢構造指数の推移(昭和32年~平成14年)
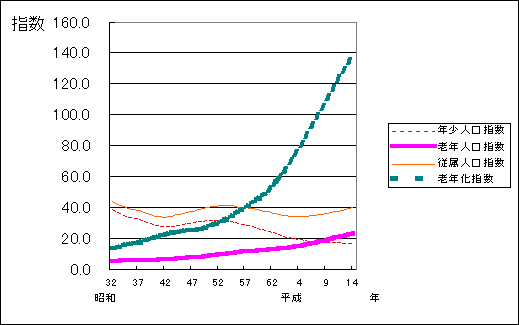
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
人口統計課 推計人口担当
03-5388-2531(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000030(at)section.metro.tokyo.jp